ヤルタ会談は1945年2月4日から11日の8日間行われ、チャーチル、ルーズベルト、スターリンは新しい世界秩序について議論し、敗戦後のドイツの統治方法、東欧の国境線、ソ連の対日参戦方法などについて決定した。
歴史学者ダイアナ・プレストンは、綿密な調査と生き生きとした文章で書かれた『ヤルタの8日間』で、戦後の世界を作り上げた8日間を記録しています。
世界大戦の混乱の中、何百万人もの避難民が移動する中、1945年2月4日から11日にかけてクリミアのリゾート地ヤルタで、弱ったルーズベルト、疲れ果てたチャーチル、そして決然としたホストで戦争中の同盟国スターリンが、新しい世界秩序について議論しました。
8日間にわたる交渉、大げさな発言、そして時折見せる親しげな態度(ソ連のキャビア、ウォッカ、シャンパンが燃料)により、3人はドイツとの戦争の終局と敗北後の統治方法について合意した。 また、発足したばかりの国際連合の憲法、ソ連の対日参戦の条件、東欧(特にポーランド)とバルカン半島の勢力圏と新しい国境線についても決定した。 会議の最後の時間、3人の指導者は、新たに解放された国々の自決と民主主義の権利を確認する「解放されたヨーロッパに関する宣言」に署名し、その後スターリンは、冬の1000マイルをモスクワに戻る装甲列車に乗り込んだのであった。 ルーズベルトとチャーチルは出発するとき、ソ連の指導者を信頼できると確信し、次の日には自国民にそう伝えることにした
しかし、スターリンは東欧に関する約束を果たすことはなかった。 わずか3ヵ月後、ルーズベルトの死後すぐに、チャーチルは新米国大統領ハリー・トルーマンに対して、「鉄のカーテン」が「前面に引かれている」と憂慮する手紙を書き、「我々の力がなくなる前にロシアと和解するというこの問題は、私には他のすべての問題を凌駕するように思える」と付け加えている。
しかし、時すでに遅しであった。 1945年夏、今度はベルリン郊外のポツダムで開かれた会議でも、スターリンにヤルタ協定を守るよう説得することはできなかった。 米国と英国は、ソ連がポーランドを含む東欧諸国への支配を強めるのをなすすべもなく見守った。ポーランドは、その自由のために英国が戦争に行き、チャーチルやルーズベルトがヤルタ会談で懸命に戦った国である。
その後すぐに冷戦が始まったため、ヤルタ会談は失敗と約束違反の代名詞となった。 2005年、ジョージ・W・ブッシュ大統領はヤルタ会談を「歴史上最大の過ちの一つ…再び、強力な政府が交渉するとき、小国の自由は何らかの形で消耗品となった」と呼びました。 しかし、結果は本当に大きく違っていたのだろうか。
ヤルタ会談の時までに、ソ連軍は東ヨーロッパの大部分を占領し、ベルリンから50マイル以内に迫っていた。 ルーズベルトとチャーチルが置かれた状況は、ロシアに併合されたクリミアや、多様な民族が国境を争っているウクライナ東部の状況に類似している。どちらの場合も、西側の指導者には、ロシアに対して道徳的圧力以外の有効な制裁手段がほとんどない。 スターリンは、「領土を占領する者は、その領土に自らの社会システムをも押し付ける」という信念に、正しい自信を持っていた。 自分の軍隊にその力がある限り、誰もが自分のシステムを押し付ける。 それ以外のことはありえない」。
チャーチルとルーズベルトの交渉の立場は、ルーズベルトの要請で会議が当初予定されていた1944年の晩夏から2度延期されていなければ、かなり改善されていただろう。1度は大統領選挙キャンペーンのため、もう1度は1945年1月の4期目の異例の就任のためだった。 1944年半ばには、ソ連軍が東ヨーロッパを占領している地域はかなり少なく、ヤルタ会談でのスターリンの立場はそれに応じて弱くなっていただろう。
すでに赤軍に占領されていたポーランドについてのヤルタ会談は、スターリンの哲学を残酷に示すものであった。 スターリンと外相のモロトフは、何時間も座っていて何も譲歩しないことから、西側代表団から「石頭」と呼ばれ、代表政府と公正な民主選挙を確保しようとするチャーチルやルーズベルトの試みを何度も挫折させたのである。 ポーランドが、チャーチルの言うように「自分の家の愛人、自分の魂の支配者」になるのは、半世紀近く先のことであった。
しかし、1945年2月の時点でさえ、ルーズベルトはアメリカの経済力をもっとうまく利用できたかもしれない。 スターリンは「この戦争で最も重要なものは機械である」と考え、アメリカは「機械の国だ…レンドリースを通じてこれらの機械を使用しなければ、我々はこの戦争に負けるだろう」と考えていた。 もしルーズベルトがレンドリース(アメリカが同盟国に「今使って後で払う」方式で装備を供給する取り決め)を撤回すると脅していたら、東ヨーロッパの何百万人もの人々のために、よりよい保護を確保できたかもしれないのです。
チャーチルが「黄泉のリヴィエラ」と呼んだ場所での会議の他の側面は、いまだに反響を呼んでいます。 ルーズベルトもチャーチルもスターリンに、勢いを増していたマンハッタン原爆計画について言及しなかった。 しかし、スターリンはスパイを通じてこの計画を知っており、西側の沈黙は彼らの不信感の一例と見ていた。 もしルーズベルトがこの新プロジェクトをもっと信頼していたら、ソ連が対日戦争に参戦し、日本占領地に侵攻するための条件をスターリンと合意することにそれほど乗り気ではなかったかもしれない-日本本土への侵攻で失われる可能性がある数百万の米軍の命を守るために不可欠だと彼は考えていた。
実際、最初の原爆実験が成功したのはヤルタ会談のわずか5ヵ月後であり、ソ連の援助の必要性が薄れていることを示した。特にポツダム会談でトルーマンが実験を公表し、その結果、スターリンがソ連軍の日本占領下の満州と朝鮮への進駐計画を前倒しで進めた。 朝鮮半島の38度線までソ連軍が進出していなければ、そしてヤルタ会談で合意された千島列島とサハリンの占領がなければ、朝鮮戦争はおそらく起こらなかっただろう。 韓国は今日、統一され民主化されているかもしれませんし、この地域で今も続いている多くの緊張も生じていなかったかもしれません。
また、あまり目立たないかもしれませんが、ヤルタ会談がいまだに響いているのは、イギリスとフランス、ひいては欧州連合との関係です。 フランス臨時政府代表のドゴール将軍のヤルタ会談からの除外に対する憤りは、彼の生涯にわたって続き、例えば、原子兵器の情報をソ連からだけでなくフランスからも隠すなど、彼が英米の覇権主義とみなすものに対して深い不信を抱かせる結果となった。 この不信感は、1966年にフランスがNATOの司令部から脱退したことだけでなく、1963年と1967年にイギリスが欧州共同体に加盟する際に拒否権を行使したことにもつながった。 1963年、彼は「L’Angleterre ce n’est plus grand chose」、つまり「イギリスはもう大したことはない」と断言した。 しかし、ヤルタ会談には、ヒトラーを打ち負かしヨーロッパ戦争を終結させるための戦略や、わずか2カ月後に初会合を開いた国際連合の構造に関する合意など、成功もあった。 ヤルタ会談で決定された安全保障理事会の拒否権の取り決めは、大国間の仲介の試みを妨げることになったが、国連は他の地域での平和維持に一定の成功を収めている。
西ヨーロッパの平和と安定のためにチャーチルとルーズベルトがヤルタで支払った代償があまりにも大きかったかどうかについては、論争が続いている。 しかし、1945年2月、彼らはもう少し上手にカードを使えたかもしれないが、どちらの指導者も最強の手腕を持っていたわけではない。 ルーズベルトは会議直後を振り返って、ある顧問に「私は結果が良かったとは言っていない」と内々に語っている。 私は、結果が良かったとは言っていない。私ができる最善のことだと言ったのだ」。
Eight Days at Yalta
by Diana Preston
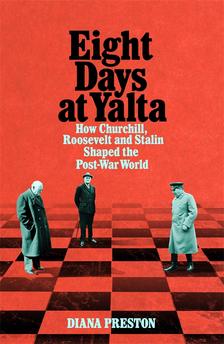
Buy the book.を購入。 Amazon, Blackwell’s, Book Depository, Bookshop.org, Waterstones, WH Smith, Wordery, Foyles
Read extract
Diana Prestonの綿密な調査による『Eight Days at Yalta』は、ヤルタ会談とその結果における激しい歴史のドラマを再現している。 大英帝国の終焉をもたらすというルーズベルトの決意から、スターリンの領土的野心まで、これらの出来事は戦後の世界を作り上げました。
この本を購入する。 Amazon, Blackwell’s, Book Depository, Bookshop.org, Waterstones, WH Smith, Wordery, Foyles
Read extract